全国対応

営業時間 8:30~17:30(土・日・祝を除く)
設置に関する法令 簡易リフト・小荷物専用昇降機
本ページでは、簡易リフトと小荷物専用昇降機の法令について解説します。
簡易リフト/労働安全衛生法
| 簡易リフトとなる 掲載中の昇降機 |
|
|---|---|
| 法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、クレーン等安全規則 |
| 区分 | カゴの面積1㎡以下 または 高さ1.2m以下で、荷のみを運搬(人は乗れない) |
労働安全衛生法において「簡易リフト」「エレベーター」という名称と、その区分が定義されています。
- 労働安全衛生法施工令(昭和47年制定)
-
- 第一条第九号(定義)
- 簡易リフトエレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
- 簡易リフト・小荷物専用昇降機・エレベーターの各区分については「労働安全衛生法と建築基準法の相違点」をご確認下さい。
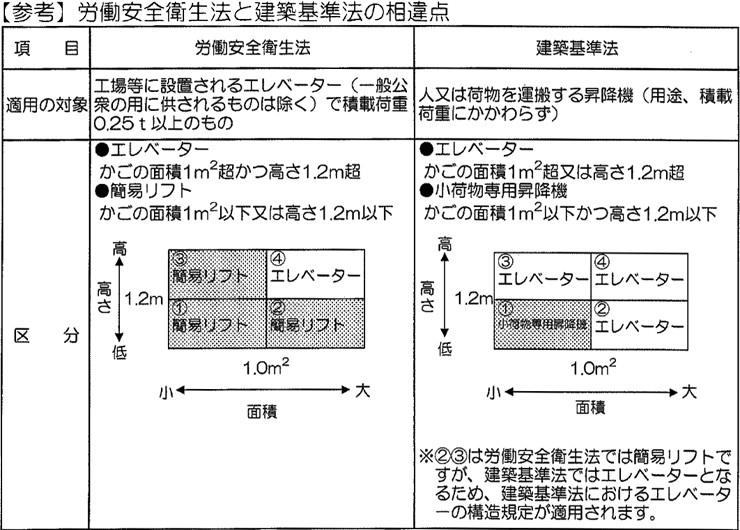
※建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年9月3日政令第310号)が公布(令和7年11月1日施行)され、①②③は労働安全衛生法では簡易リフトですので、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外とします。
簡易リフトはクレーン等安全規則において安全装置の義務、点検の義務などが定義されています。
- クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)
-
- 第一章 総則
-
- ◆第一条(定義)
-
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 三簡易リフト令第一条第九号の簡易リフトをいう。
- 第七章簡易リフト
-
- ◆第二節使用及び就業
-
-
- 第二百四条(安全装置の調整)
- 事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
-
- 第二百五条(過負荷の制限)
- 事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
-
- 第二百七条(とう乗の)制限
-
- 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
- 2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。
-
- ◆第三節定期自主検査等
-
-
- 第二百九条(定期自主検査)
- 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
- ワイヤロープの損傷の有無
- ガイドレールの状態
-
- 第二百十一条(自主検査の記録)
- 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
-
小荷物専用昇降機/建築基準法
-
区分リスト:建築基準法 小荷物専用昇降機となる
掲載中の昇降機ダムウェーター
(ADC型/ADT型/ADF型)定義する法令 建築基準法 区分 カゴの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下
※右図下図の区分①に該当するもの※区分②・③は建築基準法ではエレベーターとなり、労働安全衛生法では簡易リフトとなります。
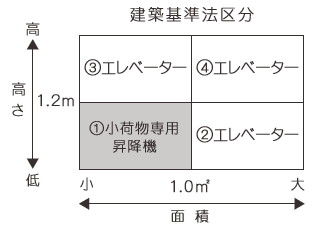
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)のメンテナンス・保守点検に関する法令
- 小荷物専用昇降機は、建築設備であり、そのメンテナンスはお客様の責任となっています。
- 建築基準法第8条において、建物の所有者・管理者または占有者は、その建築設備を「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
- 消防法について
- 消防法は、防火区画など「設置場所の環境」において昇降機と関与してくるため、昇降機の種類(簡易リフト・小荷物専用昇降機)を問わず関連します。各設置場所で関連する消防法については、総務省消防庁等でご確認下さい。
- 参考文献:
-
- 労働安全衛生法と建築基準法の相違点(※1)
- 労働安全衛生法施工令(※2)
- 労働安全衛生法(※2)
- クレーン等安全規則(※2)
- 消防法(※2)
- (※1)建築指導課より配布されている資料です。各建築指導課のホームページで内容がご確認頂けます。
- (※2)総務省が運営するイーガブ(総合行政ポータルサイト)で、各法令の検索・閲覧が可能です。
全国対応
営業時間8:30~17:30(土・日・祝を除く)


